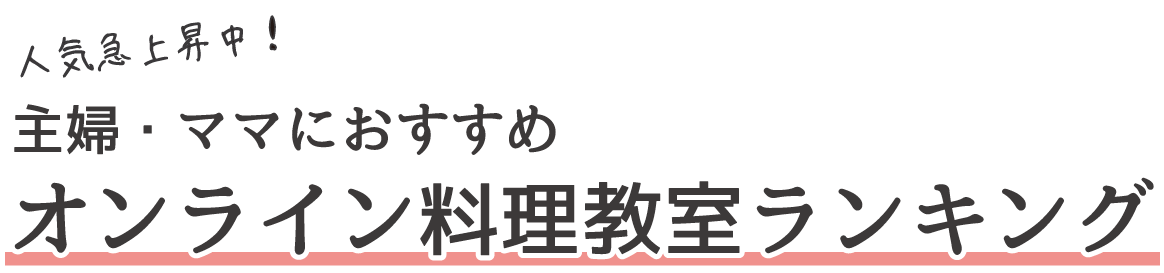料理上手になるコツ、知っていますか?
それはずばり、味見です!
私は料理が苦手だったころ、「味見しても直せないから、味見はしない!」と言っていました。しかし、それがそもそもの間違いでした。
ここでは、味見が必須な理由や正しい味見の方法、味の調整の仕方を詳しくご紹介します。
オンライン料理教室でも味見は必須!

料理上手になるためのコツとして重要な味見。それは、通学の料理教室でもオンラインの料理教室でも変わりません。
なぜ、味見が重要なのでしょうか?
- 理由①人によって「おいしい」と感じる味が異なるから
- 味見をしない人の中には、「レシピ通りに作れば必ずおいしいものが出来上がる」と思っている人がいます。
しかし、レシピは「より多くの人がおいしいと感じる味」に作ってあります。
濃い味が好きな人もいれば、薄い味が好きな人もいます。疲れている時には甘めの味付けがおいしく感じることもあります。
味見をしなければ、「レシピ通りに作った料理の味」に至るまでの過程がわからず、「自分好みの味の料理」に調整することもできません。
レシピ通りに作ったとしても人には好みがあるため、自分の好きな味にするために味見はとても重要なのです。
- 理由②舌が鍛えられるから
- 最初は、味見をしても違いがほとんどわからないかもしれません。
ですが、味見をしていくごとに甘味・塩味・酸味・苦味に対する舌が鍛えられ、「何が入るとどう変わるか」が必ずわかるようになってきます。
これがわかるようになると、「料理の味付けをどう変えたいのか」がわかるようになり、自分の好きな味のおいしい料理を作れるようになります。
なお、先日体験した和食の料理教室で、講師が「辛味は舌の感じる“痛み”であって、味ではありません」とおっしゃっていました。だからこそ、辛味を付けたい時は舌に刺激を与える唐辛子などを入れるのだそうです。
味見の方法、知ってる?知っておくとおいしくなる!
味見はなんとなく行うものではありません。
正しい味見の方法を知って、より自分好みにおいしく料理を仕上げましょう。
- 小皿にとって行う
- おいしいと感じる味には料理の温度も大きく関係しています。鍋から直接味見をするとアツアツですが、実際に食べる時には少し冷めますよね。食べる時の温度に近付けるために、味見は小皿に取って行いましょう。
- 調味料を1つ加えるごとに行う
- 調味料ごとに味見をすることで、入れた調味料による味の変化や、調味料同士の掛け合わせでどう味が変わるのかがわかるようになります。また、少しずつ入れて味見をすれば、「味が濃くなりすぎた!」という失敗を防げます。
- 味見では薄味がちょうどよい
- 小皿に少量取った味見では、ちょっと薄めの味でちょうどよい味付けになります。料理は冷める時に味が染み込むため、食卓で食べる時には味見した時よりも少し濃くなるからです。
- 何度も続けて味見をしない
- 続けて味見をするとその味に舌が慣れてしまい、味がどんどん濃くなってしまいます。味見を続けるなら多くても3度まで。それ以上の場合は水で口をゆすぎましょう。
- ある程度の量で味見をする
- 菜箸の先をちょっと舐めるだけでは味見になりません。ほんの少しだけでは味が唾液で薄まってしまうため、最低でもスプーン1杯程度は取って、しっかり味を見ましょう。
味の調整のコツ!味が濃いときに水で薄めていませんか?

私は「料理の中で味の調整が最も難しい」と思っていますが、実はこれにもコツがあります。
よくある失敗が、味が濃くなりすぎてしまうこと。
つい水を入れて薄めてしまうのですが、そうすると味がぼやけてしまってなかなかうまくいきません。
ここでは、そんな時の「味の調整方法」をご紹介します。
全体的に味が濃すぎる
水を入れるのではなく、「だし汁」や「酒」で調節します。
煮物の場合はだし汁や酒で味を薄めましょう。炒め物の場合は少量なら水を入れてもOKです。
一番簡単なのは、「具材を増やす」ことです。野菜や豆腐など、水分の多い食材がおすすめ。
砂糖を入れすぎた
砂糖の入れすぎで甘くなりすぎた場合は、和食の煮物なら「だし汁」を、洋食の煮物なら「ワイン」や「レモン汁」+「少量の塩」を入れて調整しましょう。
一番簡単なのは、「辛み成分を入れる」ことで、輪切りにした唐辛子やラー油を少量入れて甘みを調整します。
塩の入れすぎで塩辛い
つい砂糖を入れてしまいがちですが、これはNG。
塩の入れすぎで塩辛くなってしまった場合は、卵を入れて薄めたり、牛乳やみりん・酒・ごま油などを入れて味を変えたり、水溶き片栗粉を入れてとろみをつけたりして調整します。
一番簡単なのは、「少しずつお酢を加える」こと。お酢は味をまろやかにする働きがあるので、酸味を感じない程度に入れましょう。